このコラムの監修者
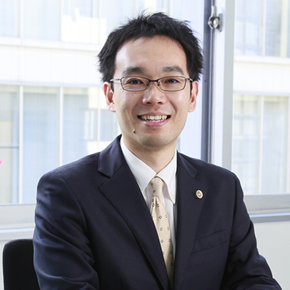
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
貞操権とは、一言でいうと「性的関係を持つか持たないかを決める権利」「性的なことがらについての自己決定権」です。
(民法で定義があるわけではありません)
貞操権侵害で慰謝料が認められるのは、「既婚者なのに独身だと騙されて肉体関係を持ち、結婚前提で交際していた」という場合が典型です。
貞操権侵害の慰謝料の相場は、50万円~数百万円とかなりの幅があります。
(交際経緯等によって異なります)
以下の記事では、まず①貞操権侵害の慰謝料とはどういうものかを解説していきます。
次に②どういうケースで認められているのかを、実際の裁判例を参考にしつつ見ていきます。
そのうえで③慰謝料問題への対法やポイントなどを紹介していきます。
(1)貞操権の中身は、性的行為をするかしないか、だけではありません。
誰と関係を持つのか、どういう性的行為まで許すのか、場所やタイミングなどといった事柄は、その人の自由意思によって決定されるべきものです。
(2)貞操権侵害は、そのような権利を侵害することです。
貞操権侵害が無理やりに(例えば暴力で)なされたものである場合、民事上の問題(損害賠償、慰謝料)だけではなく、刑事上の問題(犯罪の被害、警察の問題)にもなってきます。
※以下では、民事上の問題について解説していきます。
(3)貞操権侵害の慰謝料は、民法上の不法行為(709条)に基づくものです。
(慰謝料:受けた精神的損害(苦痛)を慰めるためのお金)
民法709条に沿っていうと、「故意過失によって貞操権を侵害した人は、それによって生じた損害を賠償する責任を負う」ということになります。
「損害を賠償する責任を負う」というのは、お金の支払いの義務があるという意味です。
精神的苦痛を賠償するお金が、慰謝料です。
(4)侵害行為が無理やりとはいえなくても、例えば「妻がいることを隠して、別の女性と肉体関係を持っていた。その女性は男性と結婚するつもりだった」といったような場合にも、貞操権侵害による慰謝料が認められる可能性があるわけです。
(1)裁判例で貞操権侵害の慰謝料が認められているのは、結婚前提の交際をしていたとか、結婚を見据えた交際をしていた、という場合が多いです(後記の裁判例参照)。
たとえば「『交際相手が既婚者だとは全く知らなかった。独身だとずっと偽っていて、それを信じて結婚前提で肉体関係を持っていた』という人が、その交際相手に慰謝料を請求した」というようなケースです。
(2)一夜限りの関係だ、相手に結婚意思がないと知っていた、身体だけの関係だ、というような場合もあるでしょう。
こうした場合は、自由意思で肉体関係を持ったにすぎないのではないか、貞操権を侵害された被害者だと言えるのか、などといった点が問題になってくる可能性があります。
(3)「結婚を見据えた交際でなければ、慰謝料は発生しない」と決まっているわけではありません。
しかし裁判例の傾向に即して言うならば、貞操権侵害の慰謝料が認められるためには、結婚前提の交際であったとか、結婚を期待するのも当然といえる経緯だったということが、求められてきそうに思われます。
(4)なお、貞操権侵害と近しい状況でいうと、たとえば「独身男女の交際で、子どもの妊娠・中絶があった。男性が不誠実な対応しかしなかった」というような場合に慰謝料を認めた裁判例もあります。
(男性が、妊娠・中絶に伴う女性の経済的・精神的負担を軽減する義務に違反したり、妊娠を避けるような方法を取るべき義務に違反したりした場合)
(1)既婚者だと知っていた場合でも、「2人の違法性(悪質性)を比較・考慮して、相手のほうが著しく大きいものと評価できるならば、慰謝料が認められる余地がある」とされています(後に挙げる最高裁判例を参照)。
ただし逆にいえば「違法性が著しく大きいとまで言えないなら、慰謝料は認められない」ということですので、その点は要注意です。
(2)この点、1つの考え方として、「交際している相手が婚姻中だと知っていれば、その人が正式に離婚しない限り自分とは結婚できないのだから、その人との結婚を期待すべきではない。期待した人を保護する必要はないから、慰謝料を認める必要は一切ない。不貞行為をした人が慰謝料請求権を得るのはおかしい」という考え方も、理屈としては成り立ちそうに思えます。
しかし、現在の裁判所は、そのようには考えていません。
(3)最高裁判所S44.9.26判決の事案では、女性が、男性が既婚者だと知って交際していたが結婚の期待を裏切られたということで、男性に慰謝料を請求しました。
この事案は、男性が、女性の年齢が若く(19歳)思慮不十分である状況につけこみ、結婚意思もないのにあるかのように装って、妻と離婚して結婚するなどと騙して肉体関係を継続させた、というケースでした。
最高裁判所は、関係を持った動機が主として男性の詐言(偽りの言葉、ウソ)を信じたためで、そのような関係になった責任が主として男性にあり、男性の側における違法性(悪質性)が著しく大きいものと評価できるときには、慰謝料請求は許容される、という判断を下しています。
(4)既婚者と知っていた場合は、不貞行為の慰謝料についても注意が必要です。
貞操権侵害の慰謝料を請求する人の立場から見ると、相手が既婚と知りつつ肉体関係を持っていたということは、相手の配偶者にその事実を知られて不貞行為の慰謝料を請求されるリスクがあります。
「相手に貞操権侵害の慰謝料を請求する」という事件とは別に(平行して)「相手の配偶者から不貞行為の慰謝料を請求される」という事件も勃発する可能性があるわけです。
(「相手が浮気を隠し通して、結果的には不貞行為の慰謝料を請求されることなく済む」ということもあるかもしれませんが、そうなるとは限りません)
さらに場合によっては、最終的に「貞操権侵害の慰謝料額<不貞行為の慰謝料額」という状況となって、経済的にデメリットが発生する可能性もありえます。
(「貞操権侵害の慰謝料を請求しないなら、不貞行為の慰謝料も請求されることはない」という保証もありませんので、慰謝料請求を控えた方が良いということでもありませんが)
貞操権侵害の慰謝料を認めた最近の裁判例としては、以下のようなものがあります。
①慰謝料50万円が認められた事例
参加資格が独身者に限定されている婚活パーティで知り合った、男性が独身者であるかのように装って肉体関係を6回持った、女性が既婚者ではないかと尋ねたが男性は否定した、という事案です。
裁判所は、女性が結婚を前提とした交際を求めているにもかかわらず、婚姻していることを秘して交際を開始して肉体関係を持つこと自体、貞操権を侵害したものであるとして、慰謝料50万円を認めました。
(別途、弁護士費用5万円が認められています。東京地裁R5.8.17)
②慰謝料90万円が認められた事例
独身者だけが利用できるマッチングサービスで知り合った、女性は少なくとも3回にわたって独身かどうかを確認した、男性は妻が居るのに独身であると積極的に欺罔して(だまして)肉体関係が通算3年あった、という事案です。
裁判所は、男性が既婚者であると認識していれば肉体関係を持たなかった、性的自由・性的自己決定権の侵害があるとして、男性が不合理な弁解に終始していること等も考慮し、慰謝料90万円を認めました。
(別途、弁護士費用9万円が認められています。東京地裁R4.6.28)
③慰謝料400万円が認められた事例
男性が既婚者であり結婚する意思がないにもかかわらずこれを隠して3年以上肉体関係を持った、交際開始当時女性は40歳で男性と出会う直前に生殖補助医療を受けるべく行動を起こしていた、男性との結婚を信じてこれを中断した、という事案です。
裁判所は、女性が真剣に子を産みたいと願っていたものと認められる、独身だという誤解に乗じて関係を継続させたこと等は悪質であるとして、女性が交際期間中に男性のために一定の支出をした(女性の主張では300万円超)と認められることも考慮し、慰謝料400万円を認めました(東京地裁R4.8.25)。
④慰謝料500万円が認められた事例
男性が既婚者であることを一切告げずに将来の結婚を約束した、2度の妊娠中絶を経て3度目の妊娠があり、男性は産んでほしいと言ったものの、実際に出産すると別れることを画策した、認知請求訴訟を提起されて初めて認知した、という事案です。
裁判所は、2度の中絶をしていること、女性が働きながら男性の子を養育していかなければならないこと等を考慮し、慰謝料500万円を認めました。
(別途、弁護士費用50万円が認められています。東京地裁H19.8.29)
貞操権侵害の慰謝料問題は、「①貞操権を侵害されたと主張する人が、相手に対して慰謝料を請求する→②交渉・協議を試みる→③合意がまとまらなければ、最終的には裁判官が、慰謝料請求権の有無や有るならその額を決める」という流れで、決着をつけていくことになります。
(1)裁判となった場合に有利な判断を得られるように、まずは証拠を探すこと、集めておくことが重要なポイントです。
証拠としては、たとえば以下のようなものが考えられます。
①交際中から今に至るまでのやりとりの内容(発言、LINE、メールなど)
・相手方が、独身だ、既婚だがすぐ離婚できる、などと説明していた際の発言
・あなたが結婚を前提にしていたこと
・2人が結婚前提のやりとりをしていたこと
②ホテルや旅行の領収書、その時の写真、日記など
・肉体関係があったことなど
③探偵の調査報告書
・相手方が既婚者であること、家庭をもっていることなど
先に見たように、裁判例をみると、結婚前提で(結婚を見据えて)交際をしていた場合に慰謝料を認めているものが多いです。
また最高裁S44.9.26判決のような事例(既婚と知って交際、結婚の期待有)の場合には、相手方の悪質性が高いことを示す証拠が重要になります。
慰謝料を請求する側としては、そういった事情があったと証明する証拠を揃えておいて、裁判に提出できるように準備しておくことが重要です。
(2)「何も証拠がない」からといって、慰謝料を請求できないというわけではありません。
訴訟では、被告(相手方)が認めている事実についての証拠提出は不要ですので、その限りでは証拠は不要ということになります。
また、たとえば当事者尋問で原告・被告が話した内容も、証拠となります。
とはいうものの、何らかの物的証拠がある場合に比べれば、慰謝料を認めてもらうためのハードルが高くなることは否定できません。
(3)慰謝料をどのように・どういう手続きで請求するかというのも、重要なポイントです。
基本的には、相手方に内容証明郵便を送付するなどして、慰謝料を請求する意思を伝えることから始まります。
手軽な方法として、メール、LINEメッセージやSMSで連絡する人も多いかもしれません。
①応答があれば、示談交渉・協議の開始となります。
示談交渉だけであれば、あなた自身で対応することも可能かもしれません。
しかし弁護士に依頼して請求したほうが、連絡を受けた相手方としては、心理的圧力を感じることが多いでしょう。
あなたが真剣に請求していることも、相手方に伝わりやすくなります。
②連絡しても相手方が全く応答してこない、応答はあったが途中で連絡が途絶えた、慰謝料を一切支払わない態度に相手方が終始している、といった場合などは、訴訟で請求することも検討しなければならないかもしれません。
特に示談交渉を弁護士に依頼していない場合には「弁護士に依頼して訴訟を提起し、慰謝料を請求していくべきか」という点を、検討する必要がでてきます。
手続きを次の段階に進めるかどうかを検討するうえで、訴えた場合の見通しだけではなく、時間、費用、労力、色々な要素を考慮することになります。
(4)相手方の反応が思わしくないからといって、嫌がらせだと指摘されるようなこと、たとえばSNSに相手方の名誉を毀損する書き込みを行うといったことは、してはいけません。
そのようなことをすると、相手方から反発されて、結局は慰謝料請求の妨げになってしまいます。
また場合によっては、弁護士から依頼を断られたり、依頼後に辞任されたりすることもあります。
慰謝料が認められるかどうかは法的な問題であって、最終的には裁判所が判断することです。
あなたがやるべきことは、裁判所に認めてもらうための最善の努力を尽くすことです。
(5)既婚と知っていた場合には、先述のとおり、相手方の違法性(悪質性)の方が著しく高いことが必要です。
裁判でそのことを証明できそうかどうか、の検討が必要です。
別の話として、相手方配偶者から不倫慰謝料を請求される可能性があります。
相手方へ慰謝料を請求することによって不倫慰謝料請求を引き起こしそうな場合には、そのリスクと天秤に掛けて、請求を実行するかどうかを決める必要が出てくるかもしれません。
たとえば、相手方本人が「貞操権侵害の慰謝料を請求するというのなら、妻に事情を打ち明けて不倫慰謝料を請求させる」と言って抵抗してきている場合もあります。
その場合、相手方は本気なのかそうでないのか、もし本気で実行してきたらどうなるのか、も考えておく必要があるかもしれません。
(1)貞操権侵害の慰謝料が法的に認められそうなのか否かを検討することが、最初の一歩です。
その判断のためには、弁護士の法律相談を受けてみましょう。
(2)有利な証拠を探すことも重要です。
たとえば、結婚を前提にしたやりとりがなかったこと、相手方に自分が既婚者だと告げていたこと、既婚だと知っている相手方の方が交際に積極的だったことを示すやりとりなどが考えられます。
(3)慰謝料が法的に認められなさそうな場合、あなたとしては請求を拒否することになるでしょう。
①相手方が慰謝料の請求意思を失わないのであれば、相手方が次の手段に移ってくることになります。
次の手段としては、弁護士から連絡してくる、相手方が調停を申立ててくる、というのが典型です。
(ちなみに調停の場合、出席しても不成立で終わる可能性も高いので、出席するかどうかは検討が必要です)
そこでも双方が折り合わないなら、相手方のほうで、訴えるかどうかを検討することになってきます。
②何らかの理由で、相手方が慰謝料の請求意思を失った場合、連絡が途絶えてそれっきり、というような形になることがあります。
(弁護士から連絡が来ない、調停不調で終了したがその後何も連絡が来ない、など)
そのままある程度の期間が過ぎると、将来的にはどこかの時点で「仮に相手方の慰謝料請求権があったとしても、もう時効だ」といえる状況になってきます。
時効に必要な期間は基本的に3年ですが(民法724条)、具体的にいつからその期間を数えるのかは、それぞれの個別事案により異なります。
相手方に弁護士がついている場合、時効になってしまう前に訴えるなどしてくる可能性が高いです。
(4)もし請求を完全に拒否するのではなく、「穏便に早期解決できるなら、ある程度の金銭を支払っても良い」などと考える場合などは、実質的な示談交渉を行っていくことになります。
示談交渉をする場合、落ち着いて冷静に話をすること、相手方の言い分に耳を傾けつつも自分の言い分をきちんと伝えること、が大切です。
それが出来なさそうな場合、たとえば「自分で話をしても請求を拒否する自信がない」というような場合には、弁護士に依頼するほうが適切です。
「高額な慰謝料を払うと約束させられてしまった」といった状況になりかねないからです。
(5)示談交渉がまとまれば、示談書を作成するなどして、きちんと最終的に解決させることになります。
「示談書に定める内容・条件だけが最終的な約束だ」ということを、明らかにしておきます。
(6)相手方の弁護士から連絡が来た場合、もし応答しないと、訴えられる可能性が出てきます。
交渉をしてみたが結果的にまとまらなかった、という場合も同様です。
もし、どうしても訴えられたくない何らかの事情があるのなら、譲歩してでも示談交渉をまとめるよう試みてみる、ということになります。
もちろん、いくら譲歩してもよいわけではないでしょうし、「この額以下で協議がまとまれば良し、まとまらなくてもそれはそれで仕方ない」と、どこかで割り切るしかありません。
(7)訴状が裁判所から届くことがあります。
いきなり訴状が届いた(訴えられた)というケースの多くは、相手方弁護士からの連絡に応答していなかったという場合です。
多くの場合、示談交渉での隔たりが大きく歩み寄り余地がないというように、裁判に移行しそうだというシグナルがあります。
訴状が届いたら、弁護士に正式に依頼して対応しましょう。
有利な結果を得るためには、裁判官に有利な心証を持ってもらうことが必要です。
そのためには、争点をきちんと把握し、言い分を法的に構成して、裁判官に伝え納得させることが大切だからです。
(8)訴訟で和解が成立しない場合、尋問を経た上で、判決という形で裁判は終了します。
判決確定前に控訴があると、控訴審(高等裁判所)で裁判が続くことになります。
「尋問は避けたい」「高等裁判所で争いが続くことは避けたい」といった場合、できるだけ和解を成立させる方向で進めていくことになります。
(9)慰謝料問題と同時に、事実上のトラブルが発生することもあります。
相手方が自宅や職場を訪問して抗議してきたり、SNSや掲示板に書き込みをしてきたり、といったようなことです。
相手方の心中は分かりませんが、あなたが話し合いに応じないから仕方なく、ということかもしれませんし、「法的手段を取っても慰謝料が認められないだろう」と思ってのことかもしれません。
事実上のトラブルについては、そうした行為をしないよう内容証明郵便で警告したり、場合によっては警察に相談したりすることが必要になるかもしれません。
「事実上のトラブルが生じるのは、法的に未解決だから」ともいえます。
示談・和解や判決という形で、慰謝料問題の最終的な決着がついていないから、不満のある側がそういう行動を引き起こす、という面があります。
事実上のトラブルを抜本的に収束させるためには、法的にきちんとした解決を目指すことも重要となります。
貞操権侵害の慰謝料問題を弁護士に依頼するメリットは、請求する側・される側どちらにもあります。
弁護士に依頼することで、「交渉がまとまらないなら訴える」という強い態度を、相手方に示すことができます。
それまで相手方が話し合いに応じない態度であったとしても、変化が生まれてくるかもしれません。
(相手方本人あるいは相手方の弁護士から、弁護士に連絡してくるなど)
そのほか、相手方と話すのを弁護士に任せることができる、訴えるという手段を取りやすくなる、裁判への対応をあなた自身で行う必要がほぼなくなる、といったメリットがあります。
慰謝料請求されるまでに話がこじれているわけですから、あなた自身で対応するのは精神的負担が大きく生活にも支障が出てくるでしょうし、不利な示談書にサインさせられたりする可能性があります。
弁護士に依頼することで、あなた自身で相手方に対応する必要がなくなります。
相手方も弁護士をつけてきて弁護士同士で話し合いが進んだり、相手方が弁護士をつけてこず請求が事実上保留となったりするかもしれません。
裁判への対応をあなた自身で行う必要も、ほぼなくなります。
貞操権侵害の慰謝料が認められる典型は、「既婚者だと全く知らず、結婚前提で交際していた」という場合です。
認められる慰謝料は、交際経緯等の事情によって、50万円~数百万円と幅があります。
既婚者だと知りながら交際していた場合でも、相手の違法性が著しく大きい場合には、慰謝料が認められる余地があります。
ただし既婚と知っていた以上、不貞行為の慰謝料が認められてしまう可能性がありますので、その点には要注意です。
以上、この記事では、貞操権侵害の慰謝料について解説しました。
ご参考になれば幸いです。
更新日:2025.10.31
このコラムの監修者
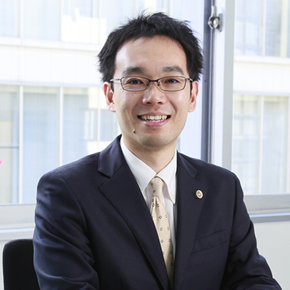
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
はじめに 不倫相手が未成年というと「えっ?」と思われるかもしれません。しかし、「女子高を出て新卒で入ってきた子に夫が手を出していた」、「大学職員である妻が、大学生と肉体関係を持っていた」というケースもありえます。 あなたが不倫慰謝料を請求するとして、いかにもお金の無さそうな未成年の不倫相手本人に請求するしかないのでしょうか。お金を持っていそうな親に請求できな・・・
要点を一言でまとめてみると: 離婚しない交際相手へ慰謝料請求(はじめに) Aに配偶者Bがいることを知っているけれど、「Aはもうすぐ離婚できるみたいだ、そうしたら自分と結婚してくれる」と思って交際を続けているCさんがいるとします。 このCさんのように、既婚者である交際相手(不倫相手)のAから「離婚してあなたと結婚するつもりだ」と聞かされていたのに・・・
別居後の不倫慰謝料請求(はじめに) 「別居して冷却期間を置いているつもりだったが、いつの間にか夫が他の女性と堂々と交際していることが発覚した」といったケースもあります。 まだ籍を抜いていないのに、夫は夫婦関係が終わったものとして行動しているわけです。 ※ここでいう別居は、別々で住んでいる状態のことです。いわゆる家庭内別居(同居はしているが会話等がない)とは異・・・
不倫・不貞行為の慰謝料の相場は? 既婚者との不倫関係が発覚すると、不倫・不貞行為の慰謝料を請求される可能性が出てきます。 「相場・判例はどれくらいなのか」「いくら請求が来るのか」と不安な悩みを抱える方も多いでしょう。 もしかしたら、500万円とか1000万円とかを実際に請求されている人もいるかもしれませんね。 不倫慰謝料は、一体どれくらいの額になるのでしょう・・・
「不倫の誓約書に仕方なくサインしたけど、もし守らなかった場合どうなるの…?」 「サインさせても、もし守らなかったら、どうしたらいいの…?」 この記事では、「不倫発覚を機に誓約書(念書)を作成したが、これに違反した」場合に起こりうる法的責任やリスク、具体的なトラブル内容を弁護士が解説します。 誓約書に違反したらどうなるのか、 金銭や損害賠償の支・・・
ラブホに入って何もなかった?(はじめに) 不倫問題に関連して、「ラブホに入ったけど何もなかったって言うんです…。そんな言い訳って通用するんですか!?」というご質問を頂くことがあります。 「ラブホテルには行ったが、不貞行為(性交渉)はなかった」「不倫・浮気はしていない」などと言い訳されたら、どうしたらいいのでしょうか? ラブホテルに入った≒性行為があった 性行・・・
はじめに 不倫慰謝料事件が解決するまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。 不倫慰謝料を請求するにせよされているにせよ、どうしても気になるところでしょう。 不倫慰謝料の標準的なケースではどれくらい時間が掛かるのか、以下で見ていきましょう。 実際には、相手方のキャラクターや対応に左右される部分も大きいです。 予想よりも時間が掛かってしまったり、話が全く・・・
はじめに(架空設例) 「不倫がバレて、交際相手の奥さん(=相手方)から呼び出されました。実は肉体関係を3年ほど続けていたのですが、2か月前からだと嘘をつきました。今後一切連絡しない、連絡したら300万を払うという誓約書を書かされましたが、示談書を取り交わしたり慰謝料を支払ったりすることはなく、その時はそれだけで話は終わりました。ところが後日、嘘がバレてしまっ・・・
「家庭に大きな不満はないけれど、どこか満たされない」 「実際に会わないなら相手を探すのは別にいいだろう。口コミも良さそうだし、無料の範囲で試してみよう」 既婚者でも、そうした軽い気持ちをきっかけに、出会い目的でマッチングアプリを使う人も少なくありません。 しかし、その気軽さ・手軽さの裏には、あなたの平穏な日常を根底から覆しかねない、「やばい」深刻なトラブ・・・