目次
はじめに
私立に進学する子どもがいらっしゃる家庭も多く、養育費としてその分を請求できるのか/支払わなければならないのか、というご質問をしばしば頂きます。養育費の算定に当たって用いられる算定表では、公立学校への進学が前提とされており、私立学校の学費等は考慮されていません。
結論からいえば、一定の場合には算定表を超える養育費が認められることもあります。
算定表と学費
公立進学が前提
私立学校に進学した場合、公立学校の学費をはるかに超える負担が生じることもしばしばありますが、算定表上は、あくまで公立学校に進学した場合が前提とされています。
具体的には、14歳以下の子については月額11,185円(年間134,217円)、15歳以上の子については月額27,820円(年間333,844円)を、教育費として考慮している形になっています。
上乗せが必ず認められるとは限りません。
そうすると、「算定表では考慮されていない以上、差額分は(例えば算定表から出てくる養育費の高い方の額が8万だとして、それに全額を)上乗せしてもらえて当然だ」と思う方もおられるかもしれません。請求する側からはある意味当然の主張とはいえるでしょう。
しかし、義務者(=養育費を支払う側)が私立学校への進学をそもそも同意していなかったというような場合、そもそも上乗せ自体が認められないこともあります(詳細は後述)。
認められるのは差額の一部です。
また、上乗せが仮に認められるとしても、差額分全額を認めてもらえるとは限りません。よくあるのは、差額分を権利者(養育費を支払ってもらう側)と義務者との基礎収入で按分して計算するという形です。養育費は双方で分担すべき費用ですので、義務者が差額分全額を負担すべき形にはならないのがふつうです。
また、このように計算した額を支払うと義務者の生活が成り立たなくなってしまうという場合、さらに負担割合が調整されることもあります。
上乗せが一部認められた事例
大阪高裁決定平成27年4月22日
長女が私立大学に進学したケースです。
もっとも、本件では、実際の私立大学の費用との差額分がそのまま認められたわけではありません。そうではなく、仮に国立大学に進学した場合にかかる費用から、算定表で考慮されている額を引いた差額の3分の1について、義務者(父)が上乗せして負担すべきものとして認められました。
ちなみにこのケースでは、①父母が結婚中に長女の進学先の高校を検討した際、国立大学への進学を視野に入れて高校を選んでいたという事情があり、また、②仮に父母が離婚しない場合であっても、長女がアルバイト等で学費を一部負担せざるを得なかったであろう(=義務者が負担すべき分が小さくなる)ことから、このような結論が出されたものです。
審判ではどのような事情が考慮されるの?
私立学校へ進学することの同意
同意があるとき
私立学校への進学について支払義務者が同意していたのであれば、基本的には上乗せが認められる方向で考慮されることが多いです。
もっとも、差額の全額が認められるかどうかはケースバイケースであり、一部のみ上乗せが認める形での審判がなされる場合も多いです。
同意がないとき
「離婚後数年経って子どもが私立学校に進学することになったが、私立に行くなんて全く聞かされていなかった」というような場合です。
婚姻費用が問題となる場面では、一応婚姻関係が続いていますので進学先の相談くらいはする(=同意があるといえる)ことも比較的多いでしょうが、養育費が問題となる場面では、離婚した父母がそのような相談をしていないことも多いため、はっきりとした同意がないということはよくあります。
この場合には、基本的には上乗せは認められないということが多いです。
同意の有無は結構微妙です。
そうはいっても、私立に行くことについての同意があるかないかというのは、実際にはかなり微妙な問題です。
例えば、義務者の父としては子どもを国公立に行かせたかったが、受験に失敗して受かったのは滑り止めの私立だけ、というのはよくあることです。この場合に「私立に行く同意はそもそもしていないから、負担する義務はない」と言う言い分が審判で通るかというと、それはいささか難しいように思われます。むしろ、滑り止めではあっても私立の受験を容認したのなら、同意があったと言われても仕方がない面もあるでしょう。
義務者の収入、資産等からみて相当な額か
前述のとおり、差額分を基礎収入の割合で分担して負担するというのが一般的ですが、その計算だと義務者の生活が成り立たなくなってしまう場合もあります。この場合は、義務者の収入、資産の状況等を考慮して、義務者と権利者の負担割合をさらに調整することになります。
まとめ
私立学校の学費等についても、義務者が私立への進学を同意していた場合や、その収入・資産の状況等からみて義務者に負担させるのが妥当だと思われる場合には、養育費として認められます。
ただし、公立との差額の全額を義務者だけが負担しなければならない理由はふつうありませんので、合理的な割合で按分するなどして計算されることになります。




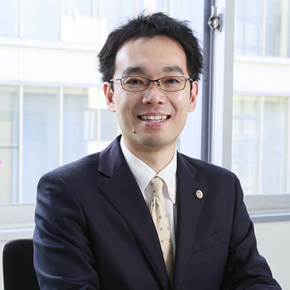





 秋葉原よすが法律事務所
秋葉原よすが法律事務所

